社労士の先生方は、日々の業務の中で「顧問先からの労務相談対応」に多くの時間を取られていないでしょうか?
有給休暇の取り扱い、育児休業、時間外労働の上限規制、社会保険の適用拡大…。
そこで注目されているのが AIを活用した労務相談の一次回答支援 です。AIにドラフトを作らせ、先生が最終チェックを行う──この工夫だけで、スピードも効率も大きく改善します。
目次
社労士が抱える労務相談対応の課題
- 同じような相談が繰り返される(有休の時季変更、育休の分割取得、雇用保険の適用 等)
- 表現の正確さが求められる(曖昧な説明は誤解・トラブルの原因)
- リサーチに時間がかかる(最新の法改正・通達を都度確認)
- 顧問先は「すぐに答えて欲しい」(迅速性も重要な価値)
この「スピードと正確性の両立」が、社労士事務所の大きな負担になっています。
AIでできること・できないこと
✅ AIでできること
- 相談内容の要約
- 関連制度の一般的な説明文生成
- よくある質問への一次回答ドラフト作成
- 難しい条文の平易化(噛み砕き)
- 顧問先向けニュースレターの下書き
❌ AIではできないこと
- 個別事案の最終判断
- 行政機関への提出書類作成や代理申請
- 法的責任を伴う助言
結論:AIは「ゼロから考える」ためではなく、“最初の一枚(ドラフト)を作る”アシスタントとして使うのが正解です。
AIを活用した労務相談一次回答の流れ
Step 1:相談内容をAIに要約させる
顧問先から届いた長文メールや口頭メモは、まず「要約」から。要点整理で見落としを防ぎます。
以下の相談文を要約してください。
- 相談の趣旨
- 関連しそうな制度や法律
- 想定されるリスクや注意点
相談文:
<<<ここに顧問先の相談内容を貼り付け>>>Step 2:AIに一次回答のドラフトを作らせる
顧問先へ返答するメールの「たたき台」をAIに作成させます。
以下の相談について、社労士事務所の一次回答文を作成してください。
- 法的枠組みを簡単に示す
- 断定は避け、一般的な考え方として説明
- 最後に「最終判断は個別事情により異なります」と添える
相談内容:
<<<ここにStep1の要約を貼り付け>>>Step 3:先生が最終チェック・修正
- 断定的すぎないか?表現は適切か?
- 顧問先の事情に即しているか?
- 最新の法改正・通達が反映されているか?
最終判断は必ず先生が行うことで、スピードと信頼性を両立できます。
実務イメージ(Before / After)
Before
- 相談メールを読む
- 法令や過去回答を調べる
- 回答文をゼロから作成(約30分)
After
- AIが要約+ドラフト
- 先生は修正・確認のみ(約10分)
- 1件あたり20分短縮 → 1日5件で100分削減
年間では、100時間以上の効率化も十分に狙えます。
品質を守るための注意点
- AIの出力をそのまま送らない(必ず人の確認)
- 免責文を必ず入れる(例:「本回答は一般的な内容であり、最終判断は個別事情によって異なります」)
- 機微情報は入力前にマスキング(個人名・企業名・細かな数値 等)
- 事務所内で利用ルールを統一(テンプレ・表現・保存先)
実務で役立つAIプロンプト集(コピペOK)
1. 育児休業の分割取得に関する相談
相談内容を要約し、関連する制度の概要と一般的な対応方針を整理してください。
断定せず「一般的に」「通常は」といった表現を用い、最後に免責文を付けてください。
相談文:
<<<相談内容>>>2. 時間外労働の上限規制について
顧問先から「月60時間を超える残業を命じてもいいか」と相談された場合の一次回答文を作成。
法的枠組みを簡潔に説明し、リスクを示した上で「最終判断は顧問先の具体的状況による」と添えてください。
状況:
<<<状況メモ>>>3. 社会保険の適用拡大に関するQ&A
パートタイマー従業員について、2024年以降の社会保険適用要件を分かりやすくまとめてください。
経営者向けに専門用語を避け、平易な言葉で説明すること。
前提:
<<<企業規模・就業形態>>>AI活用を成功させる3つのコツ
- 「下書き専用」と割り切る:最初の文章をAIに任せ、先生は判断に集中。
- 事務所共通のテンプレを作る:プロンプトや免責文を標準化し、品質を平準化。
- 成果を定量化する:対応時間、修正率、顧問先満足コメントを測り改善。
⚖️ 法律上の注意点:補助金関連の前段階支援について
補助金の「正式な申請書作成・代理提出」は行政書士の独占業務です。社労士事務所で可能なのは、情報提供・要件整理・AIによる下書き支援まで。最終申請は行政書士(または商工会)に依頼する運用が安全です。
まとめ
- 労務相談対応は「スピード×正確性」の両立が課題。
- AIは一次回答の下書きづくりに最適。
- AI → 先生チェックで効率化と品質向上が両立。
- 免責文・標準化ルールを徹底すれば、安心して活用可能。
AIを正しく活用すれば、先生は「本当に人が判断すべき業務」に集中できます。顧問先にとっても「早い・分かりやすい・安心できる」相談対応が可能になり、事務所の信頼度は一層高まります。
🎁 無料ダウンロード|労務相談AI活用チェックリスト
SORA-NEXTAIでは、社労士事務所様向けに 「労務相談AI活用チェックリスト」 を無料でご提供しています。
- プロンプト例5選
- 回答テンプレ雛形
- 品質を守るための注意点まとめ

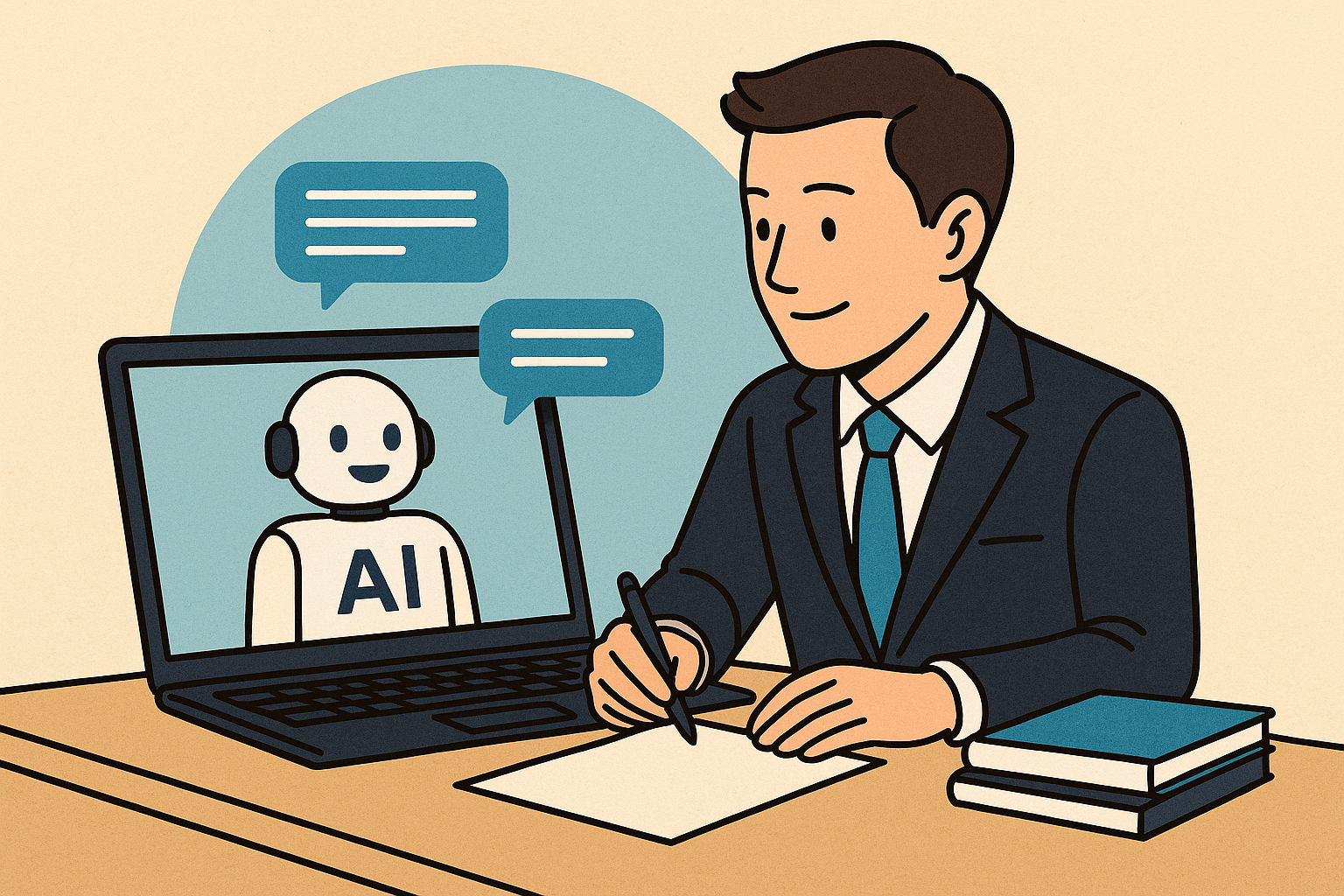
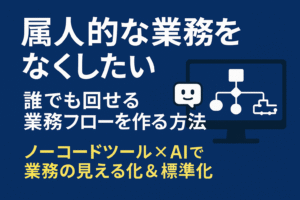
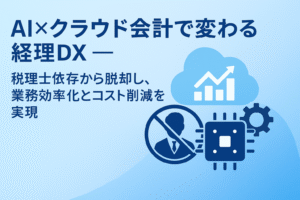


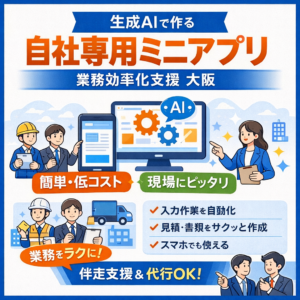

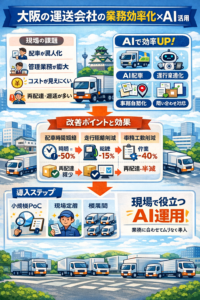


コメント